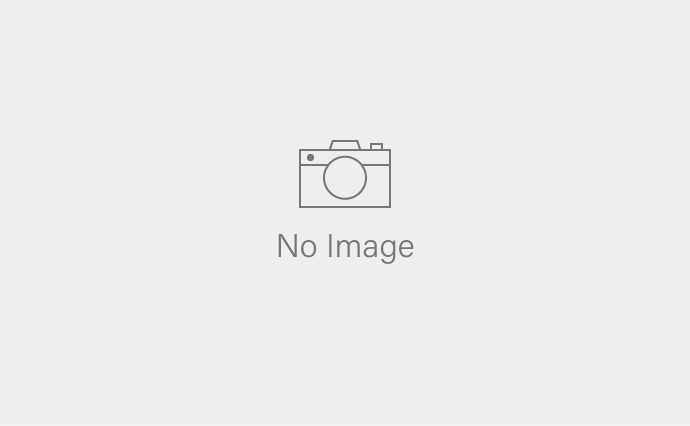変形性膝関節症
中高年の方の膝の痛みの原因のひとつです。
関節軟骨の退行性変化に起因するもので、滑膜の炎症などが生じ、関節の破壊や変形をきたします。
ほとんどが一次性。
疼痛や可動域制限、腫脹や変形を症状とします。
まずは保存療法からはじめて、日常生活に支障をきたすようになると手術療法を検討します。
保存療法は、減量(肥満がある時など)、運動療法、装具装着、薬物療法など。
よく、「膝に注射していました~」という方も多いと思います。
あとは痛み止めを飲んだりしている方も多いです。
手術療法
私が勤務していた頃(2022年頃)は、変形性膝関節症の手術といえば
人工膝関節全置換術(TKA)
単顆型人工関節置換術(UKA)
の二つが主流でしたが、最近は変わっているのでしょうか。
ここではこの二つについて、まとめます。
人工膝関節全置換術(TKA)
TKAの場合、膝関節の内側も外側も全て取り替えます。
膝全体のすり減りと変形が進行している患者様に適応されていました。
単顆型人工膝関節(UKA)
関節のすり減りが一部だけ(内側or外側)の場合に、その部分だけを人工関節で入れ替えする。
関節可動域が良好、前十字靭帯が温存されている場合が適応。
UKAのほうが膝への負担も少なく、回復も早いといわれている。
膝関節手術後の看護
私が勤務していた頃は基本的な観察項目は、メモにまとめていました。
ただ、基本的なことですので、あとは手術中の申し送りを受けて必要なことを追加していた形にはなります。
観察項目
・体温
・血圧
・脈拍
・Spo2
・呼吸苦
・四肢冷感、チアノーゼ
・咽頭痛
・麻酔覚醒レベル、左右差、手・足関節運動
・知覚鈍麻、しびれ
・心電図モニターのチェック
・創部の保護状態(膝の手術の場合、ステリーテープやカラヤヘッシブ、パーミロールで保護されていた)の確認
・ドレーンが挿入されていた場合は、ドレーン刺入部のガーゼ汚染、排液量、正常、圧の確認、クランプの有無
・硬膜外麻酔(EPI)をしている場合は、こちらも刺入部の観察
・点滴刺入部の観察や、次の抗生剤の投与時間の確認、
・全身麻酔でやる手術のため、腸蠕動音や嘔気、嘔吐の確認、
・尿道カテーテルの挿入もされていることが多かったので、尿量の確認もしていました。
・アイシングシステムの作動
ドレーンとは
術後の患者様の血腫の形成を予防するために、ドレーンが留置されます。(されない場合もありました)
血腫→感染や腫脹の増大により疼痛が引き起こされることが考えられる。
SBドレーン
吸引ボトルに風船のようなものが入っており、しぼんでいると自然圧、膨らんでいると陰圧です。
ゴム球がついているので、そこをシュッシュッと押すと吸引圧がかかります
J-VACドレーン
平たい形をしており、排液口をあけると大きく膨らみます。
排液を破棄した後は、バッグの中央を押して、排液口を閉め、下側に折り返す部位があるので
手前に曲げると吸引が開始されます。
ドレーンはつまりを予防するためにミルキングをしていました。
ミルキングとは排液が管内でつまらないように指でしごいて、流す手技になります。
CPM(持続的他動運動機械)
私が勤務していた病院では、術後数日でCPMという機械の開始になります。
ドレーンが抜けた段階で開始となっていることが多かったです。
CPMとは、関節可動域訓練をするために、横になって術側の足を機械にセットし、
一定のリズム、角度(設定できる)で曲げ伸ばしの運動をしてくれる機械になります。
大きい機械ではありますが、持ち運びは可能ですので、ベッド上で行うことができます。
複数の患者様にしようするので靴下を使用するか、タオルを敷いて感染予防をしていました。
主に私の勤務先ではタオルを使用していました。(タオルは患者様のものを使用)
・関節可動域の拡大
・循環の改善
・一定の角度、リズムによる運動で除痛
・関節軟骨の保護
が目的となります。
こちらは以前かかわりのあった医師から教えていただいたのですが、なぜ除痛されるかについては
動かすことで滑液が増える→関節軟骨に栄養される→関節がなめらかになる、疼痛軽減
だそうです。
関節軟骨は、荷重運動により、すり減り老化します。そのため、出血や疼痛の原因になります。
関節軟骨自体が、血管もリンパ管も存在しないため、栄養は滑液によってもたらされます。
滑液は関節の滑膜で作られ、吸収され循環しています。
関節軟骨の組織内の細胞まで達するためには動かすことが重要とのことでした。
ただ、術後間もなく開始となり痛いという患者様も多いので、
患者様に合わせて角度やスピードの調整をしていました。
角度に関しては医師からその患者様の目標値を提示されるので、目標値を2回超えるまで継続していました。
疼痛予防のために、施行前に鎮痛剤の投与などをしている患者様もいました。